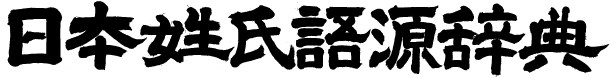ツルタ 【鶴田】レベル6
約46,200人
日本姓氏語源辞典
福岡県、鹿児島県、愛知県。続いて熊本県、東京都、佐賀県、神奈川県、山梨県、大阪府、長崎県。ツルダは稀少。
①佐賀県唐津市相知町佐里の小字の鶴田から発祥。同地に鎌倉時代にあった。
②鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田発祥。室町時代に記録のある地名。地名はツルダ。
③地形。水流田の異形。江戸時代にあった門割制度の鶴田門から。門の位置の例。鹿児島県曽於市末吉町南之郷、鹿児島県鹿屋市横山町、鹿児島県鹿屋市吾平町下名、鹿児島県肝属郡肝付町後田、鹿児島県肝属郡肝付町前田、鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠。門による明治新姓。
④鹿児島県南九州市頴娃町御領鶴田発祥。同地に江戸時代に門割制度の鶴田門があった。門による明治新姓。
⑤鹿児島県阿久根市鶴川内の小字の鶴田から発祥。同地に江戸時代に門割制度の鶴田門があった。門による明治新姓。
⑥鹿児島県曽於市大隅町須田木の小字の鶴田から発祥。地名はツルダ。同地に江戸時代に門割制度の鶴田門があった。門による明治新姓。
⑦宮崎県えびの市湯田の小字の鶴田から発祥。同地に江戸時代に門割制度の鶴田門があった。門による明治新姓。
⑧宮崎県えびの市池島の小字の鶴田から発祥。同地に江戸時代に門割制度の鶴田門があった。門による明治新姓。
⑨福岡県築上郡築上町上ノ河内の小字の鶴田から発祥。同地付近に分布あり。
⑪事物。鶴から。茨城県那珂市戸付近(旧:戸多)では江戸時代に鶴が家にたびたび飛んできた前田氏が前田の前を「鶴」にして称したと伝える。前田参照。
⑫地形。鶴と田から。山梨県山梨市(旧:東山梨郡八幡村)では寛元7年1月11日に石川氏の田に飛来した白鶴を記念したと伝える。寛元年間は1247年(寛元5年)までで寛元7年は存在しない。推定では1249年(宝治3年)。石川参照。宮崎県串間市市木では兵庫県伊丹市の出で宮崎県児湯郡高鍋町上江が藩庁の高鍋藩主の秋月氏から江戸時代に賜って平尾姓から改姓したと伝える。平尾参照。善隣。栃木県足利市県町、埼玉県深谷市横瀬に分布あり。
※秋田県仙北市角館町薗田釣田は江戸時代に「釣田新田」、「鶴田新田」と呼称した地名。同地に戦国時代に鶴田氏がいたと伝える。
⑬熊本県葦北郡芦北町大尼田の小字の鶴掛から発祥。鶴掛の「鶴」を使用。
⑭奈良県五條市西吉野町老野の小字の鶴田から発祥。地名はツルダ。
⑯コリア(朝鮮・韓国)系。推定での比率は1%以下。地形。崔を含む「鶴」に「田」を追加。埼玉県草加市で1982年4月27日に帰化の記録あり。本姓は崔。「山本」ともあり。崔参照。山本参照。他姓もあり。